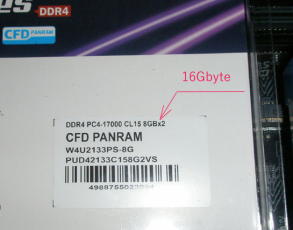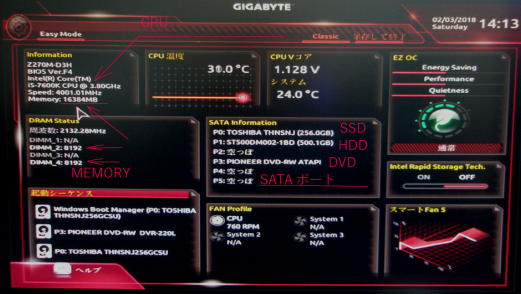DTM用パソコンを自作する、古い機材を活かす
DTM用パソコンを自作(再構築)する (2018/2制作)
■古いPCから新しいDTM用PCに再構築するときに考慮したこと。
・Windows10をOSとして使用する。
OSをWindows7からWindows10に更新する
それによりマザーボード、CPU等の変更も必要になる
・手持ちのPCパーツを利用してコストを抑える。
Windows7のPCで使用していたパーツのなかで使用可能なものは
できる限り利用する
・古いデジタルオーディオ、MIDI機器、外部音源を活かす。
過去のMIDIデータを演奏するときは当時のMIDI音源が必要になる
・DAWとしてABILITY2.5を使用する。
(DAWとは デジタル オーディオ ワークステーションの略)
・DTMに不必要なソフトはインストールしない。
■PCのOS要件
〇Windows7は2020年1月、Windows8.1は2023年1月に延長サポートが
終了するので現時点で一番長く使用できるWindows10(64bit)に
更新する(2025年10月までサポート有り)
DAWのABILITYはWindows10で動作可能
Windows10 Pro (64bit) DSP版
■PCのハードウエア要件
CPU:i5-7600K (3.8G)
〇上(i7)を見ればきりがないのでコストから1ランク落とす
最近のマザーボードは負荷に応じてクロックをアップしてくれる
メモリ:DDR4 16G(8G×2枚)
〇DTMではVSTiというソフトウエア音源を多用するので
それに見合うメモリ空間が必要
そもそもデジタルオーディオを扱ううえで広大なメモリ空間が
必要になる
USB端子の数:8個以上
〇USB接続のMIDI機器が多くある、そしてUSB2.0対応の
オーディオI/Fが存在するため
ディスプレイが2台以上接続できて表示できる情報量を増やせること
〇マザーボードのメインメモリを消費せずに複数のLCDモニタを
接続可能にするためグラフィックボードを使用する
マザーボード:GIGABYTE Z270M-D3H
〇Windows10に耐えるハードであることが第一!
〇古いPCの筐体を流用するので形状はMicroATXとする
〇PCIスロットが存在すること
(オーディオI/FボードDELTA-66を流用するため)
〇PCI-Expressx16(3.0)スロットが存在すること
(グラフィックボードGV-N640OC-2GIを流用するため)
〇USB1.1、USB2.0以上の互換USB端子が8個以上確保
〇チップセットはZ270で十分な性能レベル...
■古いPCのパーツ流用
SSD:240G
古いPCで使用していたSSDをOS、プログラム用として
Cドライブとして流用する
HDD:500G(古い演奏データが存在するドライブを流用)
DTMの演奏データ、WAVデータ、VSTi音源用
PCIスロット オーディオI/F:DELTA-66
PCIexp16 グラフィックボード:GV-N640OC-2GI
DVI 2ポート、HDMI、D-Sub 4台のモニター接続可能
CD/DVDドライブ
OSのインストールのため
筐体(ケース)
筐体の増やすことを避けているため絶対流用
マザーボードMicroATX用
■古いMIDI機器、外部音源を活かす
以前から使用している以下の古い機材を使う
PCIオーディオI/F M-AUDIO DELTA-66
USB-MIDI I/F UM-550
+--MIDI音源 SC-88
+-- CM-64
+-- JP-8080
+-- TX-7
USB接続MIDI音源 SC-8820
SD-80
USB接続ドラムパッドDTX-multi12
USB-オーディオI/F ミキサーMG-16XU
USB-オーディオI/F&MIDI音源 シンセサイザーJUNO-DS61
■以前から使用していたDAWを活かす
DAWとしてABILITY2.5を使用する。
20歳代から始めたDTM(コンピュータミュージック)は音符情報の
数値打ち込みの歴史でもありMIDIが普及してからレコンポーザ、
SSWと使い続けてきた流れからABILITYを使用しているので...
■無駄なソフトウエアを入れず負荷を軽くする
OfficeソフトはインストールしないことでDAWの動作安定と
HDDなどの容量を確保する
ウイルス対策ソフトは念のため使用する(動作負荷が軽いもの)
■PCの裏側のコネクター
■BIOS画面でCPU、メモリ、SSD、HDD、DVDが
認識されている
■Windows10のインストール
DSP版のDVDを使用してインストールするので今までの
経験上、USBにはどのポートにも何も接続しない、
グラフィックボード、デジタルオーディオボードをスロットに
装着しない。内蔵ビデオ端子にモニターを接続、PS2に
キーボードを接続、SATA端子にはSSDとCD/DVDドライブ
のみを接続した状態で行う。(不要なものはつながない)
USBのマウスはつないでおいても大丈夫と思う。
SSDは以前にWindows7がインストールされていた
Cドライブで使用してドライブなので一度パーティションを
削除して見た目で新品のようにしてから新規インストールを
実施する。(他のPCにこのSSDを接続してコンピュータの
管理でパーティションを削除する)
これによりWindows10のインストール中にSSDの全容量に
対して一つのパーティションを割り当てることができる。
Windowsのインストールにはプロダクトコードが必要で
DVDのケース(厚紙を2つ折りにしたもの)の封の付近に
シールが貼ってあり表面を平らなもので優しく削ると
小さな文字列が出てくるので それを入力する。
ローカルアカウントでインストールを進めるために事前に
ユーザーID、パスワードを決めておいた方がスムースに
作業が進む。
最近のWindowsインストールは入力箇所が少なくなり
簡単になってきた。
Windowsのインストールが終わったらマウス、グラフィック
ボードを装着して各種ドライバーをインストールする。
マザーボードのチップセット/LAN/ビデオ/オーディオ、
グラフィックボードのドライバ(ネットからWindows10用の
ドライバーをダウンロード)をインストールする。
ウイルス対策ソフトもインストールする
その後、DAWのインストール、MIDI機器のドライバーの
インストール、VSTiのインストールへ進む